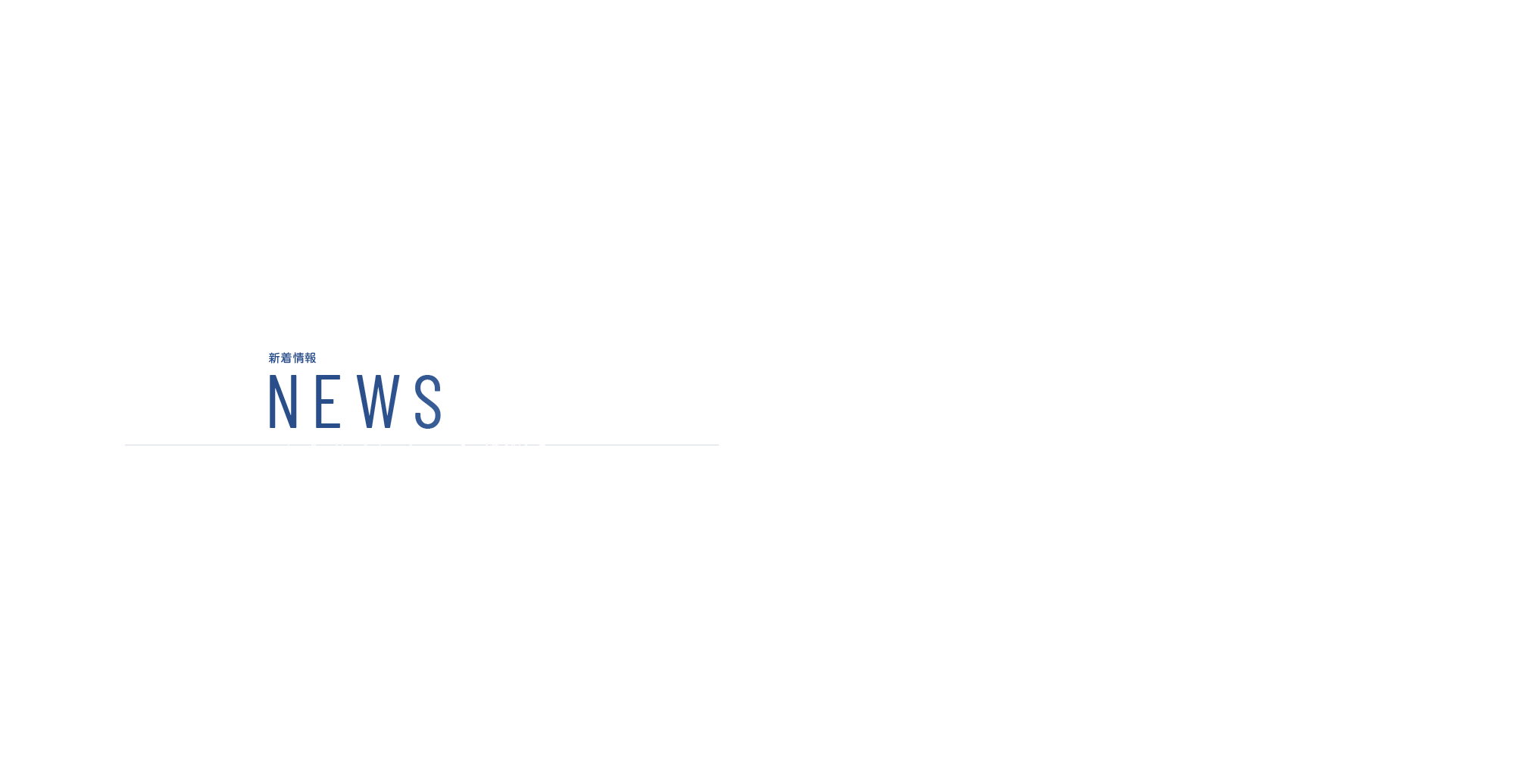
月別アーカイブ: 2025年6月
豊商事の雑学講座~起きやすいトラブル~
こんにちは、更新担当の中西です!
さて今回の豊商事の雑学講座
~起きやすいトラブル~
ということで、排水処理業でよく見られるトラブルの種類、その原因と対策について具体的に解説します。
排水処理業の現場は、水質保全と社会衛生の要となる重要な仕事ですが、目に見えないリスクや不具合が潜んでいる業種でもあります。1つのトラブルが広範囲の水質汚濁や法令違反に直結する可能性もあるため、日常的な監視と予防が不可欠です。
1. 処理水質の基準超過
■ トラブル内容
放流水に含まれるBOD(生物的酸素要求量)やSS(浮遊物質)が規制値を超えてしまう。
■ 主な原因
-
微生物活性の低下(温度変化・pH異常など)
-
負荷変動(大量の有機物や油の流入)
-
曝気不足や撹拌異常
■ 対策
-
水質測定の頻度強化とリアルタイム監視
-
自動曝気制御装置(DOセンサー)の導入
-
調整槽での負荷緩和と均質化
2. 脱水設備の詰まりや破損
■ トラブル内容
遠心脱水機やベルトプレスが汚泥の粘性・含水率により詰まりや破損を起こす。
■ 主な原因
-
汚泥濃度の急変
-
凝集剤の過不足
-
異物混入(布片・プラスチック等)
■ 対策
-
凝集条件の定期確認
-
前処理工程(スクリーン、グリット除去)の強化
-
運転マニュアルに基づく分解清掃の定期実施
3. 微生物の死滅・反応不良
■ トラブル内容
活性汚泥槽で微生物が働かず、浄化機能が一時的に低下する。
■ 主な原因
-
有毒物質(重金属、界面活性剤など)の混入
-
過剰曝気による泡立ち
-
微生物の老化(スラッジエイジ過剰)
■ 対策
-
原水中の有害物質検査の徹底
-
適切なスラッジ濃度管理
-
定期的な汚泥排出(余剰汚泥処理)
4. 配管・ポンプ類の破損や漏水
■ トラブル内容
腐食や摩耗により、配管の破裂・ポンプ停止・漏水事故が発生。
■ 主な原因
-
pH値の偏りによる金属腐食
-
異物詰まり
-
経年劣化と点検不足
■ 対策
-
耐薬品性素材の使用(PVC、ステンレスなど)
-
点検スケジュールの徹底と予防交換
-
流量センサーで異常検知
5. 異臭・泡立ちの発生
■ トラブル内容
処理場周辺や沈殿槽で異臭や泡が発生し、近隣住民からの苦情が増加。
■ 主な原因
-
嫌気反応による硫化水素発生
-
界面活性剤の混入
-
曝気量の過不足
■ 対策
-
嫌気槽の密閉・脱臭設備の強化
-
消泡剤の使用と投入量管理
-
酸素供給バランスの調整
排水処理業におけるトラブルは、機械的な故障だけでなく、“水”という変化しやすい媒体と向き合うことで生じる“見えにくい問題”が多いのが特徴です。だからこそ、日常の小さな異常を見逃さず、現場の五感と技術の力で先回りする姿勢が重要です。
![]()
豊商事の雑学講座~排水処理って?~
こんにちは、更新担当の中西です!
さて今回の豊商事の雑学講座
~排水処理って?~
ということで、排水処理の基本プロセスから最新技術、社会的意義に至るまで、丁寧に解説します。
私たちの生活や産業活動で日々生み出される「排水」は、そのまま自然界に戻すことはできません。環境を守り、健康な暮らしを維持するためには、排水処理業の存在が不可欠です。
1. 排水処理の目的とは?
排水には、生活排水(トイレ・台所・風呂など)と、産業排水(工場・飲食業など)があります。そのまま川や海に流すと、水質汚濁や生態系への悪影響を引き起こすため、法令に基づく処理が義務付けられています。
排水処理の目的は、
-
有害物質の除去
-
水質基準の達成
-
環境・地域社会の保全
という、環境保護と公衆衛生の両立にあります。
2. 排水処理の基本工程
【一次処理】物理的処理
-
ごみや砂、浮遊物を除去
-
格子(スクリーン)や沈砂池を使用
【二次処理】生物学的処理
-
微生物の力で有機物を分解
-
活性汚泥法、接触ばっ気法などが代表的
【三次処理】高度処理
-
窒素・リン・残留物の除去
-
ろ過装置、活性炭、紫外線消毒などを使用
これらのプロセスを経て、水は安全な状態で河川や海に戻される、または再利用されます。
3. 微生物の力:自然のメカニズムを活かす技術
排水処理の核心は「微生物」にあります。汚水中の有機物をエサにして、微生物が増殖・分解することで水が浄化されます。処理施設は、この自然の力を人工的に最適化した環境で運用しています。
-
適切な温度・酸素・栄養バランスの維持
-
微生物の活性化による処理効率の最大化
4. 排水処理業の現場での課題
-
汚泥の処分費用が高騰
-
設備の老朽化と維持管理コスト
-
処理水質の厳格化(環境基準の強化)
-
人材不足と技能継承の困難
これらの課題に対して、各地の業者は効率的な運転管理や再資源化技術(バイオガス化、汚泥肥料化など)を導入しながら対応しています。
5. 持続可能な社会を支える存在として
排水処理業は、単に「汚水をきれいにする」だけではありません。近年では以下のような役割も担っています:
-
再生水の農業利用や工場の冷却水への活用
-
汚泥からのバイオエネルギー生成
-
災害時の仮設処理システムの構築
つまり、排水処理業は「水資源の循環と再生」を担う社会インフラの要となっているのです。
排水処理業の仕事は、目立たずとも生活のすぐそばで私たちの環境と健康を守っています。高度な技術と誇りある使命が込められたこの仕事に、これからも社会の期待は高まるでしょう。
![]()




